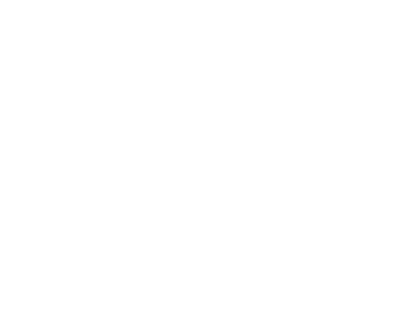Information
育児・介護休業法(育児関連)10月改正事項について
育児・介護休業法が改正されましたが、本改正は4月1日を施行日とする改正と
10月1日を施行日とする改正の2段階での改正となります。
今回は、4月1日を施行日とする改正内容のおさらいと、10月1日を施行日とする
改正の内容について記載したいと思います。なお、今回は育児関連の改正内容
についてのみ記載します。
【4月1日施行日の改正内容】
4月1日を施行日とする改正内容の主だったものは次のとおりです。
① 子の看護休暇の見直し(子の看護休暇⇒子の看護等休暇へ)
子の看護休暇が、「取得事由」「対象となる子の年齢」「労使協定による適用除外対象者」
の3点で改正されています。
「取得事由」・・従来の事由に加え、次の事由での取得が可能となりました。
1.感染症に伴う学級閉鎖等
2.入園式、入学式、卒園式
「対象となる子の年齢」・・対象となる子の年齢は次のとおり改正されました。
従来:小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)
改正:小学校第3学年修了前の子
「労使協定による適用除外対象者」・・適用除外とすることができる労働者について、
6か月未満の継続雇用要件が撤廃され、週の所定労働日数が2日以下の者のみを労使協定
により適用除外とすることができるよう改正されています。
② 所定外労働の制限の対象拡大
所定外労働(残業)の制限対象となる子の年齢が、次のとおり改正されています。
従来:3歳に満たない子
改正:小学校就学の始期に達するまでの子
③ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
こちらは努力義務ですが、3歳に達するまでの子を養育する労働者に対し、本人が希望した
場合のテレワークを月10日以上実施することが事業主の講ずる措置の対象として追加されて
います(育児目的休暇、時差出勤、フレックスタイム制の導入等は従来どおり)。
④ 育児短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
原則として3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合は、1日の所定労働時間を6時間未満
とする育児短時間勤務の措置を行う必要がありますが、業務の性質、勤務の態様から短時間
勤務の実施が困難な業務については、労使協定により時差出勤等の代替措置とすることが
認められています。本改正では、この代替措置としてテレワークを追加されました。
(なお、短時間勤務の実施が困難な業務とは、24時間体制のシフト勤務や夜間・早朝の警備、
航空機・鉄道の運行業務等とされており、どんな業務にも適用できるわけではありません)
⑤ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業へ拡大
従来の育児・介護休業法においては、従業員1000人超の企業に対し義務付けられていた
育児休業取得状況の公表が、300人超の企業規模へと対象が拡大されました。
上記が4月改正の主だった内容です。
では次に、本年10月1日を施行日とする改正内容について記載します。
【10月1日施行日の改正内容】
① 柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
10月1日改正の最も重要な内容が、この「柔軟な働き方を実現するための措置」です。
以下、「対象者」「事業主が講ずべき措置の内容」「労使協定での適用除外者」「その他事項」
について記載します。
「対象者」・・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者
「事業主が講ずべき措置の内容」・・以下のうちから事業主は2つ以上の措置を講ずる必要があります。
1.フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
2.テレワーク等
3.新たな休暇の付与(養育両立支援休暇の付与)
4.短時間勤務制度
5.保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
この事業主が講じた2つ以上の措置のうちから、労働者は1つを選択して利用することができます。
「労使協定による適用除外の対象者」・・労使協定により措置の適用を除外することができる労働者は
次のとおりです。
1.継続して雇用された期間が1年に満たない者
2.1週間の所定労働日数が2日以下の者
3.業務の性質、業務の実施体制に照らして1日未満の単位で休暇を取得することが困難な業務に
従事する者(※養育両立支援休暇を時間単位取得を認めるものとして講じた場合に限る)
「その他事項」・・会社は、労働者がこの制度の利用をする申出をしたこと、措置を利用したこと等を
理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとされています。
② 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
会社は、労働者が次の状況になったときには仕事と育児の両立に関して、個別の意向聴取・配慮を行う
ことが義務化されます。
1.妊娠・出産の申出があったとき
2.子が3歳になる前(入社時に3歳未満の子がいる場合も含む)
この意向聴取の際に、先述の「柔軟な働き方を実現するための措置」内容についても、労働者に対し
事業主が講じた措置の内容を伝え、その中からどの措置を選択するかを労働者に選択してもらう形となります。
育児・介護休業法の改正内容について、4月1日施行日の内容及びこれから訪れる10月1日施行日の改正
内容については以上となります。
【実務上の注意事項】
上記を踏まえ、実務上の注意事項について記載します。
① 就業規則(育児・介護休業について別規程としているときは、当該規程)の内容の改定
法改正に合わせ、就業規則その他規程の内容を改定する必要が生じます。既に4月の改正の際に改定して
いる場合でも、10月の内容について法改正に先だって修正していない場合は、再度の改定が必要となります。
特に、10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」については、社内の実態に合わせどの措置を
会社として選択するのか、従業員の希望も踏まえながら慎重に検討する必要があるでしょう(休暇制度は
一見取り入れやすいように見えますが、社内制度として休暇制度が既に充実していたり、人手不足により
年次有給休暇の取得も進んでいないような会社の場合、従業員から歓迎されないことも起こり得えます)。
② 労使協定の締結のやり直し
既存の育児・介護休業法に基づく労使協定を締結している場合、適用除外者等について法改正後の内容と
合わなくなる場合があります。適用除外対象者等について、改正後の内容と合わせた形での協定を再締結
する必要がある点、見落としがちなポイントとしてご注意ください。
③ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮への対応
①及び②の対応を踏まえ、既存の従業員に本改正の対象となる方がいる場合には、改正内容に関する説明と
個別の意向聴取が必要となります。
育児休業に関しては制度そのものが継ぎ接ぎとなっており、そこに改正が加わることで更に難解なものと
なっており、人事・労務機能の充実していない中小企業の中には対応に苦慮されることも多いかも知れません。
しかし一方で、人手不足が加速する時代にあってこれらの制度に会社として対応できるか否かは従業員の
採用・定着に影響を及ぼすことは否定できません。
【書式集・QA等】
育児休業に関する社内書式等については、大分労働局HP内によくまとめられたものがありますので、こちらを
ご照会します
「柔軟な働き方を実現するための措置」に関しては、厚生労働省がQ&Aを公開していますので、こちらを
参照してください。
・厚生労働省(令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年1月23日時点))