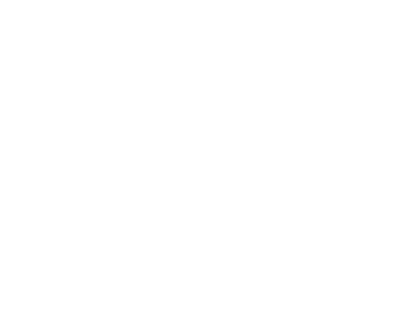Information
【安易な運用はリスクを生む?】1か月単位の変形労働時間制について
今回は1か月単位の変形労働時間制を採用する場合の適用要件や注意点について記載します。
変形労働時間制は、勤務時間を柔軟に設定できるメリットがある反面、適用要件が厳しく、しっかりした運用がなされていない場合、未払賃金の発生につながってしまいますので注意が必要です。
〇 1か月単位の変形労働時間制についての適用要件と注意点
就業規則または労使協定により適用を規定すること
1か月単位の変形労働時間制については、次の定めをする必要があります。
ア 変形期間について(1か月以内の一定の期間)
イ 変形期間の起算日(例 毎月1日を起算日とする・・)
ウ 変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
エ 変形期間における各日、各週の労働時間
オ 労使協定により採用する場合には、その労使協定の有効期間
【注意点】
(ウについて)
月の労働時間の総枠が次の計算の範囲に収まるよう、シフトを作成する必要があります。
月の労働時間の総枠=40時間(特例事業は44時間)×変形期間の暦日数÷7
特例事業以外における事業において、月の労働時間の総枠は次のとおりとなります。
| 月の日数 | 労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.14時間 |
| 30日 | 171.42時間 |
| 29日 | 165.71時間 |
| 28日 | 160時間 |
上記の時間を超えるシフトを作成した場合、変形労働時間制の適用そのものが否定されることとなります。
現実的な運用について給与の欠勤控除等を行う場合を想定すれば、上記の限度時間の範囲内で自社の設定する各シフトの勤務時間に基づいて独自の総枠を就業規則に規定するのが良いと思われます。
(エについて)
1.各日、各週の労働時間を固定して規定することが難しいとき
業務の実態から就業規則や労使協定において各日、各週の労働時間を固定して規定することが難しいことが多くあります。この場合、就業規則や労使協定においては各シフトの始業・終業時刻、組み合わせの考え方、シフト表の作成手続き、周知方法を定めます。
規定された勤務時間以外のシフト運用を行った場合、変形労働時間制の適用そのものが否定されます。必ずすべての勤務時間について規定するようにしましょう。
2.毎月のシフトが、その開始前に作成・周知されていること
各月のシフトは、変形期間の起算日として規定した日前に作成・周知されている必要があります。このため、日々の業務がその日の直前にならないと確定できないような場合、変形労働時間制の適用は難しくなります。向こう2週間程度の勤務予定が事前に確定できるようであれば、変形期間を2週間毎として就業規則に規定することは可能です。
〇時間外・休日労働、年次有給休暇の取扱いについて
よくある勘違いに「変形労働時間制を採用すれば時間外や休日労働の割増賃金の支払いは不要である」というものがあります。
たとえ変形労働時間制を採用していたとしても、時間外・休日労働に関して割増賃金の支払は必要です。
また、年次有給休暇の取得についても所定労働時間が日により異なることから通常の労働時間制と異なる取扱いをすることとなります。
変形労働時間制についての時間外・休日労働および年次有給休暇の取扱いについては、以下のとおりです。
(1) 時間外労働について
変形労働時間制の時間外労働については、「日」「週」「月」のそれぞれで把握する必要があります。
1. 「日」の時間外労働
勤務日のシフトによる所定労働時間が法定労働時間(8時間)を超えるか否かで扱いが異なります。
・シフトで定めたその日の勤務が法定労働時間を超えているとき
⇒当初定めたシフトの時間を超過した分を時間外労働とします。
・シフトで定めたその日の勤務が法定労働時間未満のとき
⇒当初定めたシフトの時間~法定労働時間までの分は「法定内時間外労働」、法定労働時間を超過した分を「法定外時間外労働」とします。
例 6時間勤務として設定した日に、9時間労働した場合
6時間(定時)~8時間(法定労働時間)分の2時間は「法定内時間外労働」
8時間~9時間(実際の退勤時間)分の1時間は「法定外時間外労働」
このとき、給与の計算時には、以下の係数で割増賃金を支給します。
「法定内時間外労働」では、時間数×通常の賃金の時給単価
「法定時間外労働」では、時間数×通常の賃金の時給単価×1.25
をそれぞれ支給することとなります(※賃金規定にこの割増率を超える定めがあるときは、当該規定に従います)
2. 「週」の時間外労働
作成・周知した勤務シフトによる週の所定労働時間が法定労働時間(40時間)を超えるか否かで扱いが異なります。
・シフトで定めた週の所定労働時間が法定労働時間を超えているとき
⇒その週の所定労働時間を超過した労働時間を「法定外時間外労働」とします。
・シフトで定めた週の所定労働時間が法定労働時間以下のとき
⇒週の所定労働時間を超え、法定労働時間までの労働時間を「法定内時間外労働時間」、法定労働時間を超過した分を「法定外時間外労働時間」として、「日」による時間外労働と同じ係数で割増賃金を支給します。
3. 「月」の時間外労働
月の総労働時間が、その月の法定労働時間の総枠を超過した場合に割増賃金の支払が発生します。
月の時間外労働も週の時間外労働同様、日による時間外労働分との重複は発生しません。
【時間外労働計算時の注意点】
「週」や「月」の時間外労働は、「日」により算定した時間外労働分は除外します。このため、一見「毎日の時間外労働だけ算定すれば、「週」や「月」の時間外労働は計算の必要がない」と誤解される方もいますが、実際の時間外労働計算時には以下の点に注意が必要です。
① 月初の週が月をまたぐ場合、最初の週は先月最終週からの所定労働時間分を含めて考える
⇒就業規則等により別段の定めのない限り、1週間は日曜を起算として考えることとされています(昭和63年1月1日基発第1号・婦発第1号)
このため、その月が例えば水曜日から始まっている場合、前月最終週の日曜~火曜の所定労働時間は当月の初週の所定労働時間に含めて計算する必要があります。このとき、その週の所定労働時間が40時間を超過するときは、その超過分を当月の時間外労働として計算する必要があります。
② その月の労働時間の累積が総枠を超過したときは、その超過分は全て「法定外時間外労働」となる
⇒特に月の最終週やその前週に起こりやすいのですが、その月の労働時間の累積が月の所定労働時間の総枠を超過した場合、その超過分は「法定時間外労働」として計算することとなります。
例 1月の最終日の所定労働時間は6時間であり、その日に2時間の時間外労働を行った。なお当該週の所定労働時間は38時間であり、休日出勤等勤務の変更もなかった。
⇒この場合、原則となる「日」の時間外労働の計算では、「法定内時間外労働」として通常の賃金の時給単価を支給すれば良いということでした。しかし、この前日までの時点で月の総労働時間が171時間であった場合はどうでしょう?この場合、最終日の時間外労働を含む労働時間8時間を足すと、月の総労働時間は179時間となります。一方、1月の労働時間の法定の総枠は177.14時間です。この場合、179-177.14=1.86時間分を法定時間外労働として割増賃金の支払が必要となります。
このように、1か月単位の変形労働時間制においては時間外労働の割増賃金計算が複雑になるため、未払賃金の発生リスクも高まることとなります。
【時間外労働に対する対応】
上述のとおり、時間外労働を法定どおりの計算で行おうとすると「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」の双方について、煩雑な計算の必要が生じます。このため、1か月単位の変形労働時間制を採用する際には、時間外労働に対する割増率を法定の内外問わず一定率(1.25以上)とすることが対策として考えられます。
割増率をすべて1.25以上とした場合、時間外労働にたいする支給額は増えることとなりますが、一方で時間外労働を抑制しようとする心理的効果が発生するため、業務内容の見直し等、業務の効率化の推進につながるメリットがあるのではないでしょうか。
(2) 休日と休日労働について
これもよくある勘違いですが、「1か月単位の変形労働時間制を採用すれば、休日は毎週与える必要がない」と思われている方がいます。
休日は就業規則等に別段の定めのない場合、変形労働時間制の採用の有無にかかわらず週に1日は付与する必要があります。
変形労働時間制を採用するにあたって、休日についても4週4日の変形休日制を採用したいと考える場合は、就業規則等についてその旨の規定を設ける必要があります。なお、4週4日の休日とする場合であっても、2週間以上の連続勤務を設ける等は、万が一の場合事業主の安全配慮義務違反を問われることとなるので避けるべきでしょう。
また、休日労働については36協定が締結されている場合には、1か月単位の変形労働時間制であってもその協定の範囲内で命じることができます。
休日労働については、その休日が法定休日か所定休日かにより割増賃金の支払における計算が異なります。特に週の勤務日数がシフトにより異なる場合には、法定休日と所定休日の区別はシフトにおいて明示した方が良いと考えます。なお、法定休日と所定休日については、原則として以下の考え方とされています。
「法定休日」について・・就業規則等に規定がある場合はその日。無い場合は、1週のうち最後の休日となった日。
「所定休日」は、法定休日以外に会社が定める休日を指します。労基法上、所定休日は時間外労働と同一のものとして扱います。
上記から、週ごとのシフトにて休日となる日がある場合は法定休日の判別もできることとなりますが、そうでないシフトを作成する場合は、あらかじめどの日が法定休日にあたるのかを示しておく必要があるといえます。特に就業規則等において法定休日と所定休日の割増率が異なる場合には、事後的に法定休日を事業主の都合で指定することはできないと解釈されています(月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の支払について、恣意的な運用が可能となってしまうため)。
なお、変形休日により4週4日の休日とする場合、月の初週あるいは最終週が1週間ないときは、当該週に法定休日を指定することはできません。
(3)年次有給休暇について
日により勤務時間が異なる場合に問題となるのが年次有給休暇の取得時の取扱いです。これについては基本的に次のように扱うこととなります。
① シフト作成前の取得申請があったとき
シフト作成前に年次有給休暇の取得申請があったときは、会社の就業規則や雇用契約書等で定める通常勤務時の所定労働時間を1日として処理します。会社の労働時間について、変形労働時間制のみを採用している場合には、通常勤務の所定労働時間について就業規則や雇用契約書に規定しましょう。
② シフト作成後に取得申請があったとき
シフトの作成後、年次有給休暇の取得申請があったときは、その申請日の所定労働時間を1日として処理します。なお、この際に夜勤業務がある会社は注意が必要です。夜勤業務は暦日をまたぐ勤務となることが多いですが、暦日をまたぐ勤務において年次有給休暇を取得した際には、年次有給休暇2日分を取得したものとして処理する必要があります※。これは休日について暦日を1日として考えるためです。夜勤業務に従事する従業員に対し、これを事前に周知していないとトラブルの素となる可能性が高いでしょう。
※8時間3交代勤務は例外的に連続する24時間を1日として認められます
〇その他1か月単位の変形労働時間制を採用する際の注意事項
上記のほか、1か月単位の変形労働時間制を採用する際の注意事項は以下のとおりです。
① 変形期間開始後のシフト変更は原則として行わない
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、変形期間開始後のシフト変更は原則として行うことができないとされています。これは1か月単位の変形労働時間制の適用要件である「各日、各週の労働時間を特定すること」に反するためです。変形期間開始後にシフト変更が行われる可能性がある場合には、その想定される事情について具体的に就業規則等に定めることが求められます(「業務の都合により変更することがある」のような曖昧な規定は認められません)
② 満18歳未満の労働者に対しての適用は制限を受ける
満18歳未満の労働者へ1か月単位の変形労働時間制を適用する場合、以下の制限を受けます。
・1日8時間、週48時間以内(変形期間を通じて平均週40時間以内)であること
・夜勤業務は原則として行えないこと
以上、1か月単位の変形労働時間制についての適用要件と注意事項について主なものをまとめました。
変形労働時間制については運用上注意すべき点が多く、運用を誤った場合にはその適用そのものが否定されます。この場合、通常の労働時間制の下で計算された賃金を支払う必要が生じるため、結果として従業員の人数、期間によっては多額の未払賃金が発生することとなります。
これから1か月単位の変形労働時間制を導入しようと考えている事業主さま、現在の運用に不安がある事業主さまは、ぜひご相談ください。
1か月単位の変形労働時間制について(厚生労働省リーフレット)